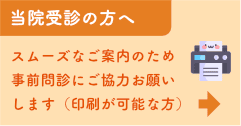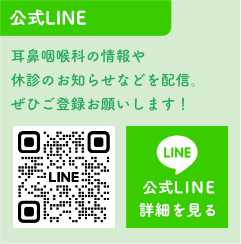鼻、花粉症・アレルギー性鼻炎
鼻の症状
こんな時にご相談ください。
- 鼻づまり
- 鼻水
- くしゃみ
- 黄色い鼻水が出る
- 鼻血
- くさいにおいがする。

鼻の病気
アレルギー性
鼻炎
アレルギー性鼻炎とは、鼻づまりや鼻水、発作的に連発するくしゃみの症状があらわれるアレルギー疾患です。アレルギー性鼻炎は、以下の2つにわけられます。
・ダニやホコリなどが原因で1年を通して鼻炎症状が認められる
「通年性アレルギー性鼻炎」
スギやヒノキの花粉などが原因で、花粉の飛散時期だけに鼻炎症状が認められる
「季節性アレルギー性鼻炎(花粉症)」

原因
季節性アレルギー性鼻炎の原因
・スギ ・ブタクサ ・ヒノキ ・カモガヤ などの花粉
通年性アレルギー性鼻炎の原因
・ダニ ・ほこり ・カビ ・フケ ・ペットの毛などのハウスダスト
花粉症を引き起こす植物の花粉飛散時期
スギ花粉1月~5月初旬まで
ヒノキ花粉3月頃~6月初旬まで
ブタクサ花粉8月頃~10月頃まで
カモガヤ5月頃~10月頃まで
参考サイト:花粉カレンダー(花粉症ナビ)
症状
アレルギー性鼻炎のくしゃみ、鼻水、鼻づまりの症状のうち、くしゃみは連続して起こり、回数が多いという特徴があります。
鼻水は、風邪などの感染症の鼻水にように粘り気があるものではなく、無色で粘り気がなく、サラサラしています。また、目のかゆみや涙が出るという目の症状を伴うこともあります。
くしゃみや鼻水などの症状により、勉強や仕事、家事に集中出来なかったり、よく眠れなかったり、イライラ したりするなど生活に支障が出ます。
そのためにアレルギー性鼻炎はしっかりと治療して症状を抑えることが大切です。
診断、検査
1.鼻の視診
鼻の中を見ることが重要です。鼻腔内所見によって、鼻水や鼻の腫れなどを診察します。
鼻の粘膜の色や鼻水の性状を観察します。
また鼻水に黄色い膿が混じっている場合は、副鼻腔炎の合併を疑い、鼻のレントゲンを撮影して確認することもあります。
2.血液検査
当院では血液の検査による血清特異的IgE検査を行っています。血液の検査によって、抗体(IgE)を調べ、アレルギーの原因物質を特定することができます。
花粉情報をチェックしましょう。
参考サイト:花粉情報はこちらから(tenki.jp)
更にきちんと飲み続ける事が、良い効果が期待できます。
治療
1.予防投与
アレルギー性鼻炎の薬を予防投与する方法があります。
効果が出るのに約2週間かかるので、花粉飛散が本格的に開始する約2週間前からの内服を勧めます。
さらにきちんと飲み続ける事で、良い効果が期待できます。
2,抗ヒスタミン薬
抗ヒスタミン薬は、体内でアレルギー症状を引き起こす「ヒスタミン」という化学伝達物質の作用を抑えることにより、症状を改善する薬です。
すぐの効果が現れますが、眠気や喉の渇きなどの副作用が起こる事があります。
最近では眠気の発現を抑えて新しい抗ヒスタミン薬も出ています。
問診による症状、今までの服用した経過などを聞き取り、ご相談して処方させて頂いてます。
3,ステロイドの点鼻薬
アレルギーによる炎症を抑えたり、アレルギーそのものを抑える薬の中で、最も強力なのがステロイドです。
でもステロイドは副作用が怖いというイメージが強いと思います。
医院で処方されているのは鼻局所投与のステロイドです。鼻局所に働いた後は、すぐに無害な物質に分解され、全身に回りませんので、安心して比較的長期に使用することができます。
1日1回の噴霧と1日2回噴霧するタイプのものがあります。
ご相談の上、処方させて頂きます。
4.舌下免疫療法
舌下免疫療法は、アレルゲン免疫療法(減感作療法)の一種で、アレルギー原因物質(アレルゲン)を少しずつ体内に吸収させることで、アレルギー反応を弱めていく治療法です。
現在、スギ花粉症とダニのアレルギー症状を根本的に治すことのできる雄一の治療法です。
ただし、治療期間が3~5年と、根気のある治療になります。治療についてはご相談ください。
治療開始時期
スギ花粉
スギ花粉に対する舌下免疫療法の治療開始時期は、6月1日~11月下旬頃です。
スギ花粉が飛ぶ可能性がある時期は、治療をはじめることが出来ません。
ただし、事前検査はいつでも行っています。ご希望の方は、いつでもご相談ください。
ダニのアレルギー
1年中、いつからでもはじめられます。
治療の効果
舌下免疫療法は、現在 スギ花粉症とダニのアレルギー症状を根本から治す雄一の治療法とされています。
しかし、すべての患者さんに効果が期待できるわけではありません。
お薬の販売前の治験では、2割が完治し、6割の方に症状の改善が見られ、2割の方は効果はありませんでした。
注意点
・最低3年間は治療を続ける必要があります。
・最初の1年間は2週間毎、2年目からは1か月毎に通院する必要が」あります。
・効果がない場合もあります。
参考サイト:舌下免疫両方(アレルゲン免役療法ナビ)
日常生活の注意
アレルギーの原因(抗原)が体に入らないように、遠ざけるようにします。
花粉が原因の場合は、マスク、眼鏡、帽子の着用。窓を開けない、頻繁に掃除機を掛ける、床は雑巾で拭き掃除をする、空気清浄機を使用するなど家の中の対策も大事です。
また洗濯物を外に干さない。家に入る前に花粉を払うなど、家の中に花粉を入れない事も効果があります。
ダニが原因の場合は、よく掃除してホコリを減らす、絨毯を避ける、寝具を干す、空気清浄機を使用する。
副鼻腔炎
副鼻腔炎とは、副鼻腔の粘膜が炎症を起こす病気で、別名「ちくのう症」と呼ばれています。
原因は、ウィルスや細菌への感染が原因となります。
その他、喘息、歯科疾患、生活環境、体質、食生活などが原因となることもあります。

症状
鼻つまり、頭痛、のどに鼻水が落ちる、頬の痛み・違和感、粘り気にある黄色い鼻水が出る、痰が絡んだ咳が出る
診断
鼻の中の鼻鏡で見れば、ほぼ診断がつきますが、症状によりレントゲン撮影し、画像診断します。
副鼻腔炎は目や脳にも炎症が広がることもあり、視力の低下や意識障害を起こす恐れもありますので、違和感がある場合は、なるべくお早目にご相談ください。
治療
鼻の中の鼻鏡で見れば、ほぼ診断がつきますが、症状によりレントゲン撮影し、画像診断します。
副鼻腔炎は目や脳にも炎症が広がることもあり、視力の低下や意識障害を起こす恐れもありますので、違和感がある場合は、なるべくお早目にご相談ください。
経過
数回程度の治療では完治しない病気ですので、粘り強く治療に取り組んで頂く必要があります。
個人差がありますが、3~6か月程度治療を継続する方もいらっしゃいます。
症状が重い方、鼻茸というポリープが出来ている方は、手術による治療も検討します。
手術を検討すべき患者さんに対しては、対応している医療機関をご紹介いたします。
鼻出血
原因
大部分は鼻の入口付近の鼻柱の粘膜より出血します。
粘膜がただれていたり、血管が浮き出ていたりしている局所的な原因が多いです。
アレルギー性鼻炎等で鼻水が入口にあり、よく噛む、こする等で粘膜が傷つきます。
子どもの鼻血の大部分はアレルギー性鼻炎でこすりすぎておきます。
血液をサラサラにする薬も鼻血を出やすくします。

検査
鼻鏡で鼻血がどこから出ているか確認します。
治療
多くの鼻血は綿球等を入れて鼻の入口をつまむか強く圧迫すれば数分で止まります。
座ってアゴを引いて止血するようにします。
止まりにくい鼻血は局所麻酔後、電気凝固で出血している血管を焼いて固めます。
日常生活の注意
・アレルギー性鼻炎等で鼻水が多い時は鼻の治療を早めにしっかりする。
・鼻をこすりすぎない。鼻の中に指を突っ込まない。
・塩分、アルコール等を控えて血圧を上げない。
嗅覚障害
臭いを嗅ぎ分ける感覚を嗅覚といいます。
嗅覚の障害には、病状や原因によって3つの病態に分類されます。

病態
1.気導性嗅覚障害
副鼻腔や鼻腔が、アレルギー性鼻炎、鼻中隔湾曲症、慢性副鼻腔炎などの病気が原因で、鼻が詰まって臭いが感じ取れなくなります。
2.嗅神経性嗅覚障害
薬剤や風邪ウィルスによって嗅覚細胞が破壊されて、臭いを感じなくなります。
新型コロナウィルス感染症で発症する嗅覚障害は、このタイプだと考えられています。
3.中枢性嗅覚障害
アルツハイマーや脳腫瘍などの脳疾患によって中枢神経に障害が起こることで、嗅覚に異常が起こります。
検査
嗅覚検査のひとつとして、静脈性嗅覚検査(アリナミンテスト)を実施することもあります。
強いニンニクの臭いのするアリナミン溶液を静脈注射して、臭いを感じるまでの時間や消失するまでの時間を測定します。また、副鼻腔の内部を観察し、副鼻腔炎が起こっていないか画像検査を用いて確認する場合もあります。
治療
副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎が原因の場合は、原疾患の治療。
アレルギーを抑える薬や抗生剤、点鼻薬などで鼻の状態が良くなれば嗅覚は回復して
いきます。アリナミンの臭いがわからないなど、臭いの神経が傷ついている場合は、治りにくいです。
神経を回復させるステロイドの点鼻薬を3カ月を限度に使用します。
ビタミン、漢方薬を処方する場合もあります。
日常生活の注意
強いにおい(香水、芳香剤など)を時々かいで、においの神経を刺激してください。
わかるにおい、程度を診察時に教えてください。
においを感じるまで時間がかかる事が多く、根気よく治療する。
風邪を引かないようにして、鼻がつまりだしたら早めに治療する。
よくいただくご質問
A:アレルギー性鼻炎には、季節性のものと通年性のものがあります。花粉症は花粉が飛散する時期だけ症状があらわれる季節性のものです。
A:スギやヒノキ以外でも、春から夏にかけて飛散するカモガヤなどのイネ科植物や、秋に飛散するキク科の植物であるブタクサやヨモギ、クワ科の植物であるカナムグラなど60種類以上の花粉が花粉症の原因と報告されています。
A:個人の体質が発症に関係しているため、完治は難しいと考えられています。治療法としては、体内のアレルゲンを取り除いてなるべく遠ざけるようにするもしくは、減感作療法によってアレルゲンを少しずつ体内に取り込み、アレルギー反応を抑制します。
A:
アレルギー薬は、花粉の飛散が少なくなるまで継続して飲む必要があります。花粉症の症状が少なくなったからといって、自己判断で服用をやめてしまうと慢性鼻炎になることもあります。
スギ花粉の飛散が少なくなってきた5月から舌下免疫療法を開始できますので、お薬を減らしたい方や薬に満足できない方にはお勧めです。
A:妊婦や授乳中の方でも処方できる安全な薬があります。安心して受診ください。該当される方は、問診票にご記載ください。
A:手術による治療も可能で、焼灼術や鼻粘膜へレーザー照射する手術もあります。
手術治療を検討される場合、対応している医療機関をご紹介いたします。
まずはご相談ください。
A:
花粉の飛ぶ2週間ぐらい前よりアレルギーを抑える薬を服用したり。点鼻したりするとシーズンを楽に過
ごせます。
花粉症を我慢していると症状が治まるまで時間がかかり、強い薬を使用しないとなかなか良くなりません。
A:アレルギーを薬で眠気がほとんど出ないものもあります。診察時に相談してください。
点鼻薬は眠気も出ず、効果もあります。
A:マスクや眼鏡を着用し、上着は表面がスベスベした素材のものが最適です。
花粉飛散情報をチェックして、花粉の多い時は外出を控えること考慮してください。
帰宅したら、屋内に入る前に花粉をよく払い、洗顔、うがいをしてください。
窓や戸のむやみに開閉を避け、部屋をこまめに掃除してください。
布団、洗濯物は外へ干さないでください。
A:掃除機は頻繁にかける事を心掛けてください。
シーツ、布団、枕カバーは週1回以上の洗濯が望ましいです。
布団の乾燥、掃除機での吸引でダニを減らせす事が出来ます。
こまめに換気して湿度50%以下が望ましいです。
カーペット、畳よりフローリングが望ましいです。
A:急性副鼻腔炎が疑われます。レントゲンで鼻の副鼻腔に膿が溜まっていないか診断
します。細菌をなくする抗生剤、鼻汁の出るのを減らす薬、痛み止め頓服、局所洗浄、ネブライザー吸
入等で治療します。早く治療すれば2~3週間前後で治りますが、人によって慢性化
する事もあります。
A:アレルギー性鼻炎と副鼻腔炎と両方かかっている場合が60%前後あります。
アレルギー体質の強い方は鼻汁が止まりにくく、風邪を引くとすぐ副鼻腔炎が再発した
り、悪化しやすいです。風邪を引かないように気を付けましょう。
アレルギー性鼻炎への治療も同時にしなければならない場合も多いです。
根気よく治療していかなければなりません。